Ryukoku Museum
龍谷ミュージアム秋季特別展
「博覧 -近代京都の集め見せる力-」
初期京都博覧会・西本願寺蒐覧会・
仏教児童博物館・平瀬貝類博物館

「博覧」とは趣味や研究、社会の発展のため、ある種のモノや資料を広く集め、一般に公開するという意味です。そして、その催しが博覧会であり展示会で、その常設の機関が博物館です。
幼い頃、夢中になって小石や貝殻、切手やコインを集め、そのコレクションを友人と見せ合い、楽しんだ記憶はありませんか?その思いは好奇心や満足感から、時には探究心へと膨らんでいくこともあります。
明治時代から昭和戦前期にかけて、京都で開催された博覧会や展示会、開設された博物館では、様々な手法を用いて展示資料を集めていました。さらに、見せ方(展示手法)や意匠(展示造作)にも工夫を凝らしていました。
本展では集め見せる試みとして、日本初の「博覧会」と称された「京都博覧会」、明治初期から継続された浄土真宗の法灯を伝える、大規模な展覧会「西本願寺蒐覧会」、仏教を児童に伝える博物館「仏教児童博物館」、京都で先駆的な自然史系博物館「平瀬貝類博物館」を取り上げ、当時の主催者側の、展示に込めた強い思いを探りたく思います。
展示構成
- 第1章:
- 初期京都博覧会
- 第2章:
- 西本願寺蒐覧会
- 第3章:
- 仏教児童博物館
- 第4章:
- 平瀬貝類博物館
会期・開館時間
会期
2022年9月17日(土)~ 11月23日(水・祝)
休館日:月曜日、9月20日、10月11日
(ただし、9月19日、10月10日は開館)
開館時間
10:00 ~ 17:00
※入館は16:30まで
※10月7日、10月21日は20:00(入館は19:30まで)
入館料
- 一 般 1,300(1,100)円
- 高大生 900(700)円
- 小中生 500(400)円
- 小学生未満:無料
- 障がい者手帳等の交付を受けている方、およびその介護者1名:無料
(手帳またはミライロIDを受付にてご提示ください)
※( )内は前売り・20名以上の団体料金
【リピーター割引】
本展のチケット半券のご提示で2回目のご入館時、入館料金300円引き!
(他の割引との併用不可。ご本人・本展のみ)
【Sonoligo対象展覧会】
本展は、イベントサブスクリプションサービスSonoligoに登録しています。Sonoligoとは月額定額制で登録された有料イベントに追加料金なしで参加できるサービスです。(同一イベントへの参加は最大2回まで)
主催・特別協力・後援
- 主催
- 龍谷大学 龍谷ミュ ー ジアム、京都新聞
- 特別協力
- 浄土真宗本願寺派、本山 本願寺
- 後援
- 京都府、京都市、南あわじ市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、
南あわじ市教育委員会、(公社)京都府観光連盟、
(公社)京都市観光協会、NHK京都放送局、KBS京都、エフエム京都
出品リスト
関連イベント
| 開催日 | イベント名 | 場所 |
|---|---|---|
| 8月11日(木・祝) | プレ記念講演会 講師:北田 克治 氏 | 龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室 |
| 9月18日(日) | 学芸員トーク | 龍谷ミュージアム101講義室 |
| 9月23日(金・祝) | 西本願寺書院・飛雲閣拝観ツアー | (集合)龍谷ミュージアム101講義室 |
| 9月25日(日) | 記念講演会 講師:多田 昭 氏 | 龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室 |
| 10月2日(日) | 記念講演会 講師:佐藤 優香 氏 | 龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室 |
| 10月7日(金) | ナイトミュージアム ギャラリートーク |
龍谷ミュージアム展示室 |
| 10月8日(土) | 学芸員トーク | 龍谷ミュージアム101講義室 |
| 10月9日(日) | 記念講演会 講師:並木 誠士 氏 | 龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室 |
| 10月15日(土) | ワークショップ 貝を使ったリース作り |
龍谷ミュージアム101講義室 |
| 10月21日(金) | ナイトミュージアム ギャラリートーク |
龍谷ミュージアム展示室 |
| 10月22日(土) 10月23日(日) |
文化財修復について知ろう! 日本画の原料や作り方を知ろう! |
龍谷ミュージアム101講義室 |
| 10月29日(土) | ワークショップ 天然鉱石から岩絵具を作ろう |
龍谷ミュージアム101講義室 |
| 10月29日(土) 10月30日(日) |
文化財修復について知ろう! 日本画の原料や作り方を知ろう! |
龍谷ミュージアム101講義室 |
| 11月3日(木・祝) | 学芸員トーク | 龍谷ミュージアム101講義室 |
| 11月13日(日) | 記念講演会 講師:和田 秀寿 | 龍谷大学大宮キャンパス東黌301教室 |
| 11月20日(日) | 西本願寺書院・飛雲閣拝観ツアー | (集合)龍谷ミュージアム101講義室 |
| 11月16日(水)~ 11月23日(水・祝) |
『もう一度、「博覧」 』クリアファイルプレゼント New | 龍谷ミュージアム受付 |
| 11月19日(土) 11月20日(日) |
「関西文化の日」記念 クリアファイルプレゼント New | 龍谷ミュージアム受付 |
| 11月23日(水・祝) | 『ありがとう「博覧」』一筆箋プレゼント New | 龍谷ミュージアム受付 |
◆ プレ記念講演会
「南極観測越冬隊の1年間」 私の南極生活と天然石集めのきっかけ
- 日 時
- 8月11日(木・祝)13:30 ~ 15:00
- 会 場
- 龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室
- 講 師
- 北田 克治 氏
(第38・45次南極観測隊越冬隊料理人、レストラン「赤おに」店長兼料理長) - 定 員
- 先着100名
※ 聴講無料/観覧券不要/龍谷ミュージアムHPから事前申込が必要
◆ 記念講演会
①「貝を集める面白さ 平瀬貝類博物館に思う」
- 日 時
- 9月25日(日) 13:30~15:00
- 会 場
- 龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室
- 講 師
- 多田 昭 氏(元香川県立津田高等学校教諭)
- 定 員
- 先着150名
※ 聴講無料/観覧券必要(観覧後の半券可)/龍谷ミュージアムHPから事前申込が必要
②「仏教児童博物館-モノを介したコミュニケーション」
- 日 時
- 10月2日(日) 13:30~15:00
- 会 場
- 龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室
- 講 師
- 佐藤 優香 氏(東京大学大学院情報学環客員研究員)
- 定 員
- 先着150名
※ 聴講無料/観覧券必要(観覧後の半券可)/龍谷ミュージアムHPから事前申込が必要
③「京都における博覧会と西本願寺」
- 日 時
- 10月9日(日) 13:30~15:00
- 会 場
- 龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室
- 講 師
- 並木 誠士 氏(京都工芸繊維大学特定教授・美術工芸資料館館長)
- 定 員
- 先着150名
※ 聴講無料/観覧券必要(観覧後の半券可)/龍谷ミュージアムHPから事前申込が必要
④「特別展回想 列品解説と共に」
- 日 時
- 11月13日(日) 13:30~15:00
- 会 場
- 龍谷大学大宮キャンパス東黌301教室
- 講 師
- 和田 秀寿(龍谷ミュージアム学芸員)
- 定 員
- 先着150名
※ 聴講無料/観覧券必要(観覧後の半券可)/龍谷ミュージアムHPから事前申込が必要
◆ ワークショップ
①「貝を使ったリース作り」
- 日 時
- 10月15日(土)
①11:00~12:30、②15:00~16:30 - 会 場
- 龍谷ミュージアム101講義室
- 講 師
- 大谷 洋子 氏(西宮自然保護協会理事)
- 定 員
- 各回先着10名
※ 参加費1名500円/当日の観覧券必要(当日の観覧後の半券可)/龍谷ミュージアムHPから事前申込が必要
※ 小学校低学年の方が参加する場合は、保護者が付き添い、ご参加ください。(付き添いのみの参加は無料)
②「天然鉱石から岩絵具を作ろう」
- 日 時
- 10月29日(土)
①11:00~12:30、②14:00~15:30 - 会 場
- 龍谷ミュージアム101講義室
- 講 師
- 米田 寿恵 氏(龍谷大学先端理工学部研究補助員[森 正和研究室])
- 定 員
- 各回先着10名
※ 参加費1名800円/当日の観覧券必要(当日の観覧後の半券可)/龍谷ミュージアムHPから事前申込が必要
※ 小学校低学年の方が参加する場合は、保護者が付き添い、ご参加ください。(付き添いのみの参加は無料)
※ 企画 森 正和(龍谷大学先端理工学部)
◆ 文化財修復について知ろう!・日本画の原料や作り方を知ろう!
西本願寺書院(国宝)「虎之間」にある「杉戸絵」の復元展示を通して、文化財修復についてわかりやすくご紹介します(パネル展示)。
また、鉱石から作った絵具でも、鉱石の砕き方(粒子の大きさ)で発色が違います。日本画の絵具の元となる鉱石を触ったり、ルーペで観察してみましょう。
- 日 時
- 10月22日(土)、23日(日)29日(土)、30日(日)
10:00~17:00 - 会 場
- 龍谷ミュージアム101講義室
※ 参加無料/入退場自由/事前申込不要
※ 協力 有限会社 川面美術研究所
※ 企画 森 正和(龍谷大学先端理工学部)
◆ 京都博覧会・西本願寺蒐覧会の舞台裏 西本願寺書院・飛雲閣拝観ツアー
京都博覧会・西本願寺蒐覧会の舞台となった本願寺書院を、龍谷ミュージアムの学芸員が解説を交えながらご案内します。
- 日 時
- 9月23日(金・祝)、11月20日(日)
①9:30~11:00、②13:30~15:00
- 集合場所
- 龍谷ミュージアム101講義室
- 定 員
- 各回先着20名
※ 参加費1名500円/当日の観覧券必要(当日の観覧後の半券可)/龍谷ミュージアムHPから事前申込が必要
◆ 学芸員トーク
- 日 時
- 9月18日(日)、10月8日(土)、
11月3日(木・祝)
13:30~14:00 - 会 場
- 龍谷ミュージアム101講義室
- 定 員
- 当日先着30名
※聴講無料/当日の観覧券必要(当日の観覧後の半券可))/事前申込不要

◆ ナイトミュージアム・ギャラリートーク
10月7日(金)、10月21日(金)は20:00
(入館は19:30)まで開館時間を延長します。
また、18:30より展示資料の見どころを解説するギャラリートーク(事前申込必要・聴講無料・当日の観覧券必要(当日の観覧後の半券可))を展示室で開催します(45分程度)。
- 定 員
- 先着20名
※ ギャラリートークの時間は会場が解説で騒がしくなります。ご了承ください。

※ ワークショップ「天然鉱石から岩絵具を作ろう」、文化財修復について知ろう!、日本画の原料や作り方を知ろう!、京都博覧会・西本願寺蒐覧会の舞台裏 西本願寺書院・飛雲閣拝観ツアーは、下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」令和4年度採択事業です。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況により、予定を変更することがあります。最新の情報は 龍谷ミュージアムHPをご確認ください。
シアター上映
ミュージアムの3階には、ミュージアムシアターを設置しています。
200インチのスクリーンで大迫力の映像をご覧ください。
※17:00~の上映は、10/7(金)、21(金)の開館時間延長時(20:00閉館)のみ実施しています。
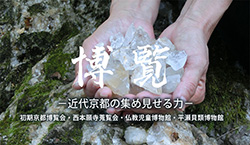
特別展『博覧』序章 (約11分)
秋季特別展「博覧」の4つの柱について解説します。また主な展示資料についての見どころをわかりやすくご紹介します。
上映開始時刻
10:30/11:00/12:00/12:30/13:30/14:00/15:00/15:30/16:30/17:00 ※/18:00 ※/18:30 ※/19:30 ※

「伝えゆくもの ~西本願寺の障壁画~」(約12分)
西本願寺・書院の障壁画にスポットをあて、復元模写された障壁画の美しさをご覧いただくとともに、肉眼では識別できなかった、描かれた当時の「虎之間」竹虎図を写真とCGによって紹介します。
上映開始時刻
11:30/13:00/14:30/16:00/17:30 ※/19:00 ※
展覧会図録
2022年度秋季特別展
「博覧 -近代京都の集め見せる力-」
初期京都博覧会・西本願寺蒐覧会
仏教児童博物館・平瀬貝類博物館
- 龍谷ミュージアム、京都新聞 発行
- A4版 260頁
- 定価:2,500円(税込)
展示を担当した学芸員が10数年間調べ上げた4つのテーマ、初期京都博覧会、西本願寺蒐覧会(しゅうらんかい)、仏教児童博物館、平瀬貝類博物館についての集大成版。展示会場では記せなかった多くの内容が集録され、図版はなんと415点にも及び、黒を基調とした重厚な展覧会公式図録。
博覧会や展覧会の主催者たちは目的を達成するために、どのように資料を集め展示に工夫を凝らしたのか。その詳細をお手にとって熟覧ください。
通信販売も承ります。詳細はこちら
